★★★ 2018年10月18日(土) プラネットスタジオプラスワン
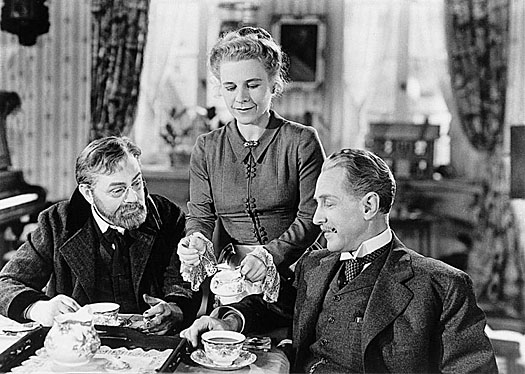
ドイツの細菌学者、パウル・エーリッヒの伝記映画です。
監督のウィリアム・ディターレは、この数年前に「ゾラの生涯」というエミール・ゾラの伝記映画でアカデミー作品賞を獲ってるので、伝記ならディターレってことで呼ばれたんでしょうが…まあ、普通の映画であります。
展開の佳境は2回来る。
1回目はジフテリアの特効薬発見ですが、このときは若いってこともあり、制止も聞かずに新薬を病床の子供たちに打ちまくります。子供たちは回復し副作用もなくめでたしめでたしで、患者の中に政府要人の子供もいたりして研究予算もゲットするのであった。
で、2回目だが、壮年期に梅毒の特効薬を開発する。はやく商品化しろと押し寄せる病院や医院の医師に対し、副作用の確認のため1年待てと言う。若い時のジフテリアとえらい違いで、まあ年食って保守的になるのは仕方ないのだが、映画としてはもう少し上手くこの変心というか人間の老成を描いてもよかったんじゃなかろか。
「おんどれは研究室にいて患者と向き合ってないから悠長なこといってられんじゃボケ」
とまでは言わずとも似たようなことを言われてエーリッヒは薬を市場に出す。
そして、やっぱり副作用で死者が出る。
で裁判だが、今の感覚からいうとどうなん?という感じで無罪になりますが、しっくりこないところだ。
伝記映画といえば、数年前に「グレンミラー物語」を再見して、ああ、これはミラー本人と同じくらいに妻をフィーチャーした夫婦の年代記なんだなって改めて思った。
伝記を映画として熟成させるには、そういった何かを添加しないとしんどいんだと思う。
特殊撮影ってことでロバート・バークスがクレジットされている。
カラー期のヒッチコック映画の撮影監督で「鳥」とか「北北西」を撮った名カメラマンだが、特殊撮影って顕微鏡で見える細菌の画くらいしか見当たらないんだが。
主人公の妻のルース・ゴードンは後年ハル・アシュビーのカルト作「少年は西を渡る」のおばあちゃん役の人。
例えば妻への愛とか同僚との友情とかのドラマを起動させる要因が希少なので淡泊で味気ない。2度の流行病特効薬開発が佳境だが博士の治験対応は真逆なのに映画はそこを攻めてくれない。裁判の経緯も付け足し感横溢。ロビンソン以外のキャストも弱かった。(cinemascape)